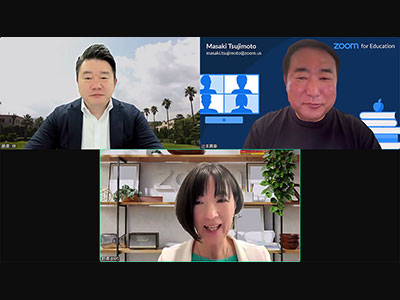校務における活用で意識したい「ガイドラインの柱」


(1)人間中心:最終判断・責任は人間にある



(2)情報漏洩への留意:環境と規約・ガイドラインを確認する



- 児童・生徒・教職員の氏名、成績、住所、連絡先、学校固有の内部情報などは入力禁止。
- 利用規約を確認し、「入力データがAIの学習に利用されるかどうか」を事前に把握すること。無料版や個人利用アカウントでは、入力内容がモデルの改善に使われるケースもある。
- 機密性の高い内容を扱う場合は、必ず管理職や情報担当に相談すること。

(3)説明可能性:出力をそのまま使わず、吟味して修正する